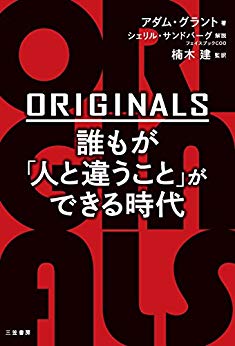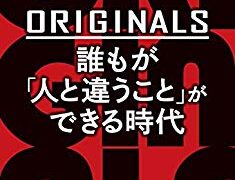part1 変化を生み出す「創造的破壊」 「最初の一歩」をどう考えるか
業績の達成には「コンフォーミティ(同調性)」と「オリジナリティ(独自性・独創性)」の2種類がある。
オリジナリティを発揮することで企業ワービー・パーカーは年商1億ドル(約100億円)を達成した。
オリジナルな人は「斬新で実用的なコンセプト」を考えだし、「自らのビジョンを率先して実現させていく」
そして誰でも「オリジナル」になることは可能である。
ある企業の離職率調査で、元々PCに入っている、インターネットエクスプローラーやサファリを使っている従業員は離職率が高いということが明らかになった。
グーグルクロームや、ファイヤーフォックス等ブラウザを自分の好みに切り替えて使っていた従業員は、離職率が低く、業績も高かった。
つまり、ありものではなく自らよりよいものがないかを探し、行動する人間は離職率が低く、成果もあげている。
だが、人間はありものを受け入れる方が心が落ち着く習性があるため、ありものを受け入れている人間がほとんどである。
最低所得者の方が「経済格差はしかたがないもの」として受け入れているとういデータがある。
つまり貧乏人は「現状を支持して受け入れる」傾向があるということ。
また、子どものころに神童、天才といわれてる子どもほど、実は突出した成功を収めていないことがわかっている。
頭がよくルールの枠組みでなんでも、うまくこなすことができるため、オリジナリティが育まれづらいのが原因。
しかし、逆に、ありもの、既存のものを疑うことこそがオリジナリティである。
ワービー・パーカーの場合はメガネの値段に何故、こんなにも高いのだろう?と疑問を持ったことが成功につながっている。
また、成果を求める気持ちが50%程度になると逆に創造性が低下しオリジナルティが生まれにくくなることがわかっている。
目標を達成しなければという気持ちが強いと、髪を染めたり、奇抜な格好をするなど、うわべだけのオリジナルを求めてしまいがちなので注意しなければならない。
オリジナルとリスク
大成功を収めた企業家は極端なリスクを取って成功したイメージが強いがそれは間違っている。
実は、リスクを極力取らず、自分のアイデアの実現にも疑問を持っている人が起こした会社の方が存続する可能性が高いという研究結果がでている。
事実、アップルのスティーブ・ウォズニアックは大企業で働きながら創業したし、、グーグルのラリー・ペイジは会社経営よりも大学の博士号を優先しようとしていた。
リスクの分散を行いながら慎重に行動することで安心感が生まれ、それがオリジナルを発揮する自由となる。
まとめ
既存のものに疑問を持ち、リスクのバランスをとりながら、行動できる人こそがオリジナルな人である。
そして、それは自分の意志で実践することが可能である。